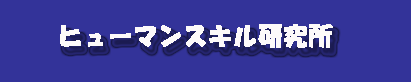■ 自立と共生
CS神戸は、民間の中間支援NPOとして様々なプロジェクトを擁しているが、その一つに起業研究員という制度がある。いわばインターンシップのようなもので、研究員に実際に様々な事業の企画運営に携わってもらい、その間にNPOに関する知識やノウハウを身につけ、ネットワークを作り上げながら起業につなごうとするものである。
さて、CS神戸のコンセプトは「自立と共生」である。この「自立と共生」を、1年間 の起業研究員の体験から少しアプローチしてみたい。
■ 自立の促進
◆ かたち
起業研究員になると、早速一人ずつ事務机と事務用品が用意され、パソコンや電話、ファクスなどの事務環境が整えられる。まるで新入社員の気分だ。同時に自分の名前の 入った名刺が手渡される。そのときの中村理事長のコメントはこうであった。「ここでは じっとしていても何もありません。地域の課題は何か、あなたは何がしたいのか、何ができるのか、この名刺を使ってどんどんアクションを起こしてください。そのバックアップを私たちは全面的に行います!」
一から教えてもらおうと思っていた私の背中を、受身から攻めへと強く押された。
整備された事務環境と肩書きのついた名刺。NPOの世界にソフトランディングできる自立のためのツールである。「自立」を意識に訴えるだけでなく、“かたち”から仕掛 ける。CS神戸の「自立」への人材育成が起業研究員の初日から始まった。
◆ しかけ
CS神戸では、概ね月一回、知的暴力バーという1000円会計の楽しい飲み会が催され、様々なテーマで口角泡飛ばす熱い議論が展開される。そのとき一人ひとりに発言が求められる。私には、もともと「わきまえの美学」というものがあった。体よく言えば、ストレートに自分を出さなくてもいつか人はわかってくれるという虫のいいものである。
最初の2~3ヶ月は参加者の高い問題意識に圧倒され、押し黙っていたが、あるとき発 言を促された。NPOは多くの人の参加を得て課題を共有し、ともに解決を図ることに活動の意味がある。そのためには、まず正直に自分をさらけ出すことが前提になる。自分の考えや意見は、素直に相手に伝えるべきだと。はたまた、飲み会という“しかけ” でNPOの何たるかを学び、自立への背中を押されたのである。
◆ 装置
CS神戸には、毎日のように起業の相談者が訪れる。起業研究員には、相手の了承を得てその場に陪席させてもらえるという特典がある。ここで社会の現実を知り、NPO活動を具体にイメージすることができる。相談では、ミッションのすり合わせがていねいに行われる。NPOのミッションは、地域に何らかの課題があり、人々が困っている 現実があって生まれる。でないと、私企業の顧客志向のアイディアやベンチャーの起業相談と変わらないからである。
一方で、NPOは有償性が基本となる。熱きハートだけで活動は成立しないし、継続もできない。シーズの確認、活動拠点や仲間の確保、資金や損益分起点など、マネジメント資源の一つひとつが明らかにされていく。
NPO活動を確かなものにする、ぶれないミッションとマネジメント力。この2つの重要な要素を、陪席という“装置”で学習していくのである。
■ 共生の実現
◆ フラットな組織
CS神戸では、スタッフが肩書きや職名で呼び合っているのを聞いたことがない。全員が「さんづけ」である。食事や飲み会はすべて割り勘。会議のときの席も決まっていない。何より情報の共有化が徹底している。外部とのやりとりや懸案事項は、リアルタイムでメールなどで共有される。何と私たちのような起業研究員に対しても、である。
肩書きで発言したり、会議で自分の席が決まっていたりすると、思考や行動が固定化してしまう。組織論理より一人の人間としての生き方が問われる時代である。人間の能力差なんて、ほとんどない。それぞれの持ち味が認められ、活かされていると実感すれば、いい加減な仕事はしないし、斬新なアイディアも生まれる。CS神戸でユニークな事業が次々と生み出されるのも、このゆえんではないだろうか。
NPO活動に不可欠な主体性や当事者性は、日ごろのフラットな職場風土によって醸成されることがよくわかる。そのことで、組織が有機的に機能するのである。
◆ 対等の関係
この起業研究員制度は、対等の関係という点からもよくできている。月額 15000円の授業料を取って、スタッフと同じように仕事をさせる。その経験が自分の血となり肉となる。研究員は授業料を払っている分、貪欲に吸収しようとするし、CS神戸もこの制度を一つの事業、一つの仕事として捉え、適当にあしらうようなことはない。
対等の関係はハッピーハッピーの関係であり、それがパートナーシップを形成する。
この関係は、NPOにおけるサービスの利用者と提供者とのあるべき姿につながる。
どんなサービスにもコストはかかる。そのサービスを維持継続しようとすれば、一定の対価は必要であろう。利用者にとってサービスが無償ならうれしい反面、言いたいことがいえないこともある。しかし、有償ならきちんとものが言える。提供者も対価を払 って選ばれる立場になることで、仕事の質そのものが磨かれる。
起業研究員制度は、この対等の関係をベースに、地域の課題を仕事という切り口で解決しようとする、新しい働き方、新しい公共の形態を示唆している。
◆ 誰もが主役
起業研究員のおもしろさは、現場での実学にある。阪神御影市場の一角にある、給食宅配サービスの「あたふたクッキング」で実習させてもらった。ここは、阪神淡路大震災の被災者による炊き出しサービスがきっかけでできた事業所である。当時、全国から 駆けつけてくれた多くの人たちに私たちができることはないか。料理なら......。この被災者とボランティアの人たちを「炊き出し」で紡いだのがCS神戸であった。
料理の好きな人が料理を作れば、配達は車の運転の得意な人がする。できる人ができることをするのがNPO。自分の車を持込み、一食につき 100円が自分の収入。届けた ときに安否確認を行い、やさしい言葉を交わす。これが活動の付加価値。ささやかなビジネスとさわやかな自己実現のマッチングが繰り広げられる。
食材は、安売りのスーパーではなく、自分たちの活動拠点であるこの商店街で調達する。地域の経済が、こんな形でゆるやかに循環しているのに気づかされる。
入り口のところには書架が施され、多くの図書が並べられている。ちょっとしたまちの図書館だ。高校生がふらっと立ち寄って本を見ている。その高校生に買い物客が何気なく話しかける。管理する人は誰もいない。本を持ち帰る人もいるらしいが、持ち込む人も多くいる。性善説をベースに、地域のやさしい顔の見える空間がここにある。
与えられる満足よりも、自分自身が何らかの形で関わることの喜びや達成感の深さ。
誰もが主役の共生社会をめざして、人と人、人としごと、そして人と地域を紡ぐのが中間支援NPOのCS神戸の真骨頂なのだ。